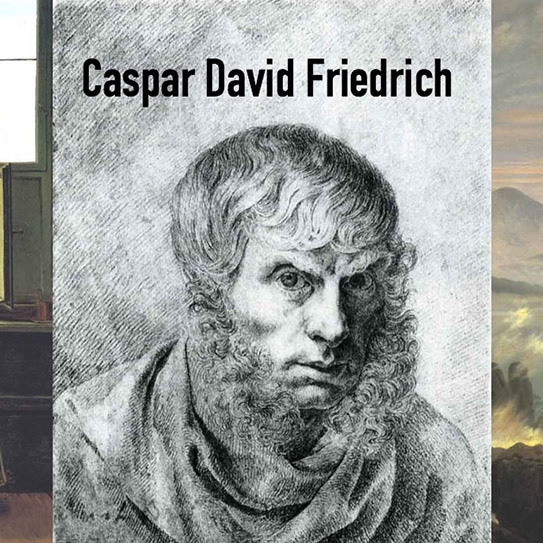
「雲海の上の旅人」解説。特集:カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ
ドイツロマン派の画家カスパー・ダーヴィト・フリードリヒの代表作品『雲海の上の旅人』を関連する作品を交えながら解説。画像有り。
雲海の上の旅人



これらの作品から発展してきた、旅人が岩の上から彼方の山を眺める構図。
前作では「虹」や「十字架」などの象徴となるファーカスポイントがあるが、本作は、大きく描かれた旅人の背中自体が、一番のファーカスポイントとなっている。
後姿の人物は、カスパーの作品には多く登場するが、鑑賞者が自己投影しやすく、鑑賞者がこの人物と同一化し、作品の中に入り込む。このドイツの古装束を着た人物たちは、後姿に描かれ、なんの行動もしていない。つまり、政治的にも自然的にも、受動的に描かれている。また、たいてい現在を意味する夕暮れ時に描かれ、その先の新たな光=未来を見つめている。
カスパーの作品には、この人物のように、ドイツの古装束を着た人物が描かれるが、これは愛国者や民主主義者が好んで身にまとった。この衣装は、解放闘争を戦ったものや、大学生、画学生らが、抵抗と連帯のしるしとして、祖国の理想像を掲げる義務のしるしとして、シンボルとなっていた。1819年には、反体制派による、暗殺事件も起こるなど活動がエスカレート。大臣会議の決議により、「煽動者(デゴマーク)」らは迫害、弾圧され、ドイツの古装束はデゴマークの衣装であるとして禁止された。

ドイツ古装束をまとった二人の男が描かれているが、まさにドイツ古装束が禁止された年に製作された。フリードリヒ自身、1820年にアトリエに来た友や他の画家に、「この人物たちは、煽動(デゴマーク)の画策をしているのです。」と皮肉をこめて語っている。
ただし、本作「雲海の上の旅人」がデゴマークの意味を込められているかは定かではない。
この男が毅然として見つめる遥かなる山の頂 = よりよき未来はやってきたのだろうか。カスパーはたまに、過去の作品、イメージを反復して描く。
1830年ごろ描かれた。

二人の男は一組の男と女に変わり、色使いやタッチも明るくなっている。前作と比べてみると、周囲の緑も若々しく生い茂り、空も夕刻だったのが夜明けを思わせる色合いになっている。1830年にはフランスでは七月革命、ドレスデンでも市民の蜂起事件が起こり、拘置者の解放や憲法の制定に至った。





